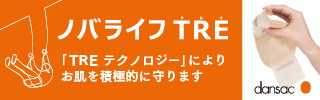ご挨拶
このたび、2025年9月6日(土)、第56回東京ストーマリハビリテーション研究会を開催させていただくことになりました東京女子医科大学消化器・一般外科の小川真平です。この歴史ある研究会の当番世話人を拝命したことは、大変な名誉であるとともに身が引き締まる思いです。開催にあたり、ご支援を賜りました世話人および関係各位に厚く御礼を申し上げます。
ストーマケアの歴史を紐解いてみますと、人工肛門のアイデアが生れたのはルイ14世時代の1710年、フランスのAlexis Littr'eが鎖肛で死亡した新生児を解剖し閉鎖部位より口側の腸管を体外に誘導すれば救命できたであろうと示唆したのが最初といわれています。また、本邦においては、人工肛門を意味する最古の訳語は1832年に記録がある「義肛」で、遅くとも1892年には造設された記録があります。それから、先人たちによって、造設法、装具、合併症対策など日々工夫や改良が行われ今日に至っています。
継承や経験に依る医療ではなく科学的エビデンスに基づく医療(evidence-based medicine:EBM)が提唱されてから四半世紀、現在ではEBMは医療の大前提となっています。しかしながら、ストーマケアは個々の患者さんの病状や価値観、周囲を取り巻く環境なども考慮することが必要な個別化医療の要素が大きく、EBMに依らない経験則に基づいた対応が必要になることが少なくありません。治療に難渋している患者さんを目の前にした時、「どう対応すべきなのか」と悩むことは誰にでもあります。先人(先輩)たちも同じような思いで問題に立ち向かい、あらゆる手段を講じながら解決の糸口を見つける、臨床ではこのようなことが繰り返し行われており、私たち医療従事者は患者さんから多くのことを学んでいるのです。
今回のテーマを、「患者さんから学び患者さんに還元するストーマケア」といたしました。研究会では、困ったことや上手く行かなかったことなどを持ちよって皆で話し合い、また、エキスパートから経験やノウハウを教えてもらうなどして解決策を導き出す、そして患者さんに還元する、そのような会にできればと思っております。
皆様のご参加を心からお待ちしております。スタッフ一同、力を結集して皆様をお迎えする所存です。どうぞ、宜しくお願いいたします。
第56回 東京ストーマリハビリテーション研究会
当番世話人 小川真平
(東京女子医科大学 消化器・一般外科)